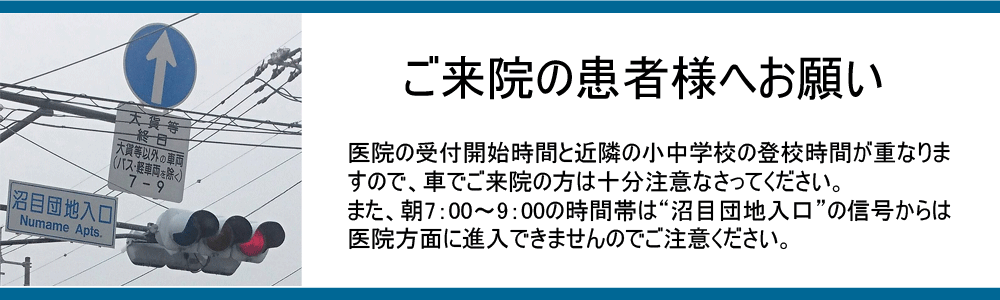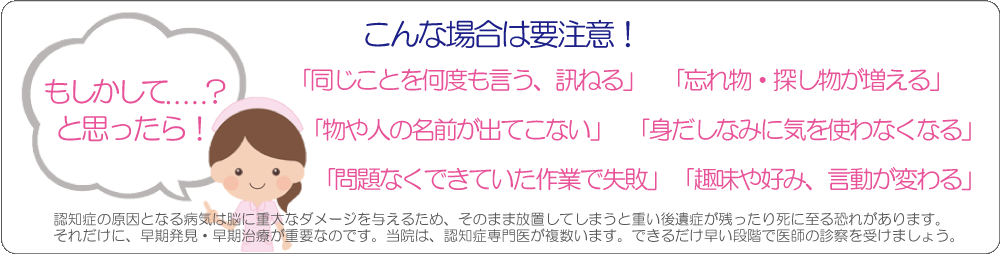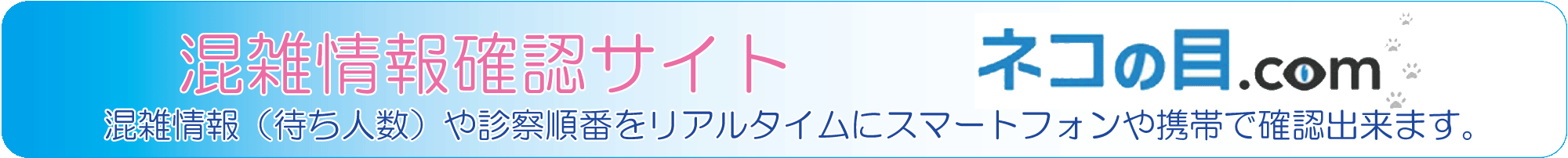
当院からのお知らせ
〇東内科ドックミニについて詳細はこちら
2024年7月1日~9月30日の3ヶ月間、東内科ドックミニを実施しております。
大変ご好評をいただいておりますので、10月1日以降も期間を延長して実施いたします。
電話予約(0463-93-1311)が必要となります。空きがある場合は、当日予約も可能となります。
〇伊勢原市乳がん検診について
今年度の伊勢原市乳がん検診は、7月から翌年2月までの毎週火曜日午後に当院では実施しております。事前のご予約が必要となります。電話受付時間は9:00~12:00、15:00~17:00となります。
尚、レディースドックにつきましては、通年行っております。
〇健康診断について
今年度の伊勢原市/秦野市/平塚市/社会保険被扶養者の特定健診を6月から開始しております。予めご予約が必要です。
〇発熱で受診を希望される方へ
発熱で受診を希望される場合は、必ず事前にお電話をお願いいたします。受診までの待機方法など、ご対応についてお伝えします。
〇新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を実施しますが、詳細は未定です。
〇お問い合わせ時間について
08:00~09:00、12:00~14:30の時間帯は、受付業務や昼休み交代などで特に電話がつながりにくくなっております。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんがご了承ください。
〇駐車場を含めた病院敷地内での禁煙にご協力をお願いします。
インフルエンザワクチン接種のご案内
インフルエンザワクチン接種の予約は不要です。
診療時間内であれば、接種可能です。
価格:4,000円(税込)
○ 64歳以下の方は下記よりインフルエンザ予防接種予診票を印刷し、ご記入の上持参してください。
《伊勢原・平塚・厚木・秦野在住の65歳以上の方は、一部公費負担で接種可能です》
接種期間
伊勢原市/秦野市:2024年10月1日~2025年1月31日、平塚市:2024年10月15日~2025年1月31日、厚木市:2024年10月7日~2025年2月28日
価格(自己負担)
伊勢原市/平塚市/秦野市:1,600円、厚木市:1,500円
帯状疱疹を予防するワクチンについて
日本人成人の9割以上が帯状疱疹を発症する可能性があります。
50歳以上の方が対象となります。特に以下の方にお勧めしております。
① がんや自己免疫疾患などの免疫機能が低下する基礎疾患がある。
② 最近、疲労やストレスが溜まっていたり、睡眠などの生活リズムが不規則であると感じる。
※ 帯状疱疹を一度発症すると免疫がつき、その後はなりにくいとされています。ただし、加齢などで免疫低下した場合は発症することがあります。
〇 事前のご予約が必要となります。2ヶ月間隔で2回の接種が必要となり、価格は税込22,000円/回で合計44,000円です。
会社の健康診断で再検査が必要な方へ
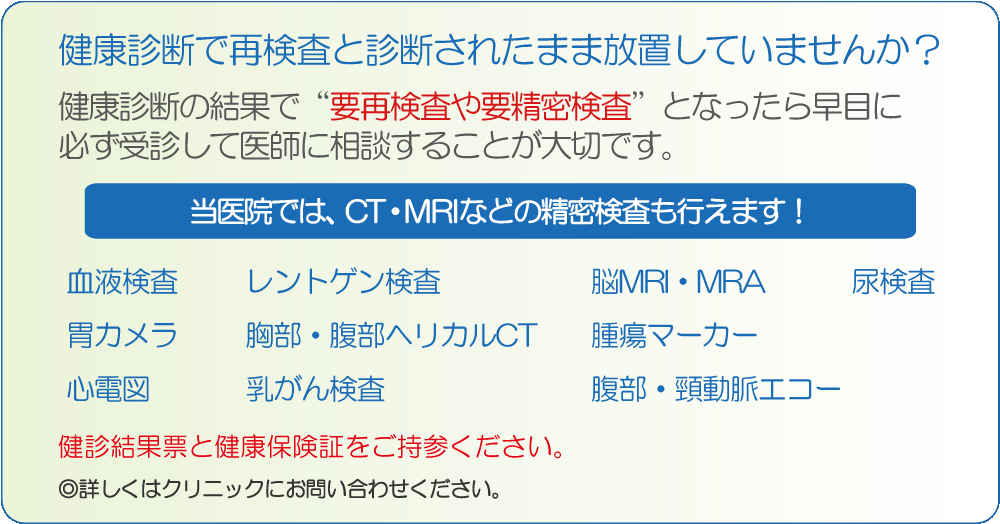
発熱外来について
慢性疾患を有する方やご高齢の方が多いので、感染予防対策のため下記の要領にて実施いたします。
① 午後の診療時間内に受付順でお受けします。土曜日は13:00~15:30です。(第4土曜日は午後休診のため、実施しておりません。)
② 発熱で受診を希望される場合は事前にお電話をお願いいたします。
③ 混んでいて順番までにお時間をいただくことがありますが、院内での待機はできませんので、一旦ご帰宅いただくか、お車の中でお待ちいただくことになります。可能ならばご家族の方が受付にいらして順番をとっていただくことをお勧めします。
④ 予め問診票をダウンロードのうえ記入してご持参いただくようお願いいたします。(ダウンロードできない方は来院時記入いただきます。)問診票はこちら
代表的な認知症の初期症状について
麻疹風疹混合ワクチン(MRワクチン)接種について
全国で相次いで麻疹の感染が広がるなか、ワクチンの供給が不安定になっています。
ワクチンの供給が安定するまで、不安な方には抗体検査をお受け頂くことをお願いしております。
高齢者等の肺炎球菌予防接種について
対象者は、65歳の人で伊勢原市・秦野市・平塚市に住民票を有し、過去に1回(自費接種も含む)も肺炎球菌ワクチンを接種されていない方が該当します。
接種期間:65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで 費用:3,000円(税込)
事前予約は必要ありませんが、ワクチンの状況により当日接種ができない場合があります。当日は接種券をご持参ください。
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 08:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 14:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休診日:木曜・日曜・祝日〔各種保険取扱〕 ※土曜日の診療時間は下記の通りとなります。 午前 8:00~11:00 午後13:00~16:00 (第4土曜日の午後は休診となります) |
||||||
○ 初診の方は17:45までに受付をお願いいたします。
○ 紹介状・健康診断結果・人間ドック結果などをご持参された方は、受付時にご提出くださいますようお願いいたします。
受付時間のお知らせ
受診の方
AM: 月・火・水・金〔08:00~12:00〕/ 土〔07:45~11:00〕
PM: 月・火・水・金〔14:00~18:00〕/ 土〔12:45~16:00〕
その他
- 伊勢原市乳がん検診について
- 今年度の伊勢原市乳がん検診は、7月から翌年2月までの毎週火曜日午後に当院では実施する予定です。事前のご予約が必要となり、6月17日(月)から予約受付を開始いたします。電話受付時間は9:00~12:00、15:00~17:00となります。
尚、レディースドックにつきましては、通年行っております。 - 帯状疱疹を予防するワクチンについて
- 50歳を過ぎたら、帯状疱疹ワクチンをお勧めします。詳しくは医院にお問い合わせください。
尚、2ヶ月間隔で2回の接種が必要となります。※価格(税込):22,000円/回(合計44,000円) - Googleストリートビュー詳細はこちら
- 院内をGoogleストリートビューでご覧いただけます。
- 風しん予防接種の一部助成について
- 先天性風しん症候群の発生を防ぐため、伊勢原市では予防接種法に基づく定期予防接種外で予防接種を受ける場合の費用を一部助成しています。助成対象者は、妊娠を予定、希望している20歳以上の女性及び妊娠中の女性の配偶者となっています。
車でご来院の患者様へ
路上駐車は近隣の方の迷惑となりますのでお止めください。
駐車中はエンジンを止め、アイドリングストップにご協力をお願いいたします。
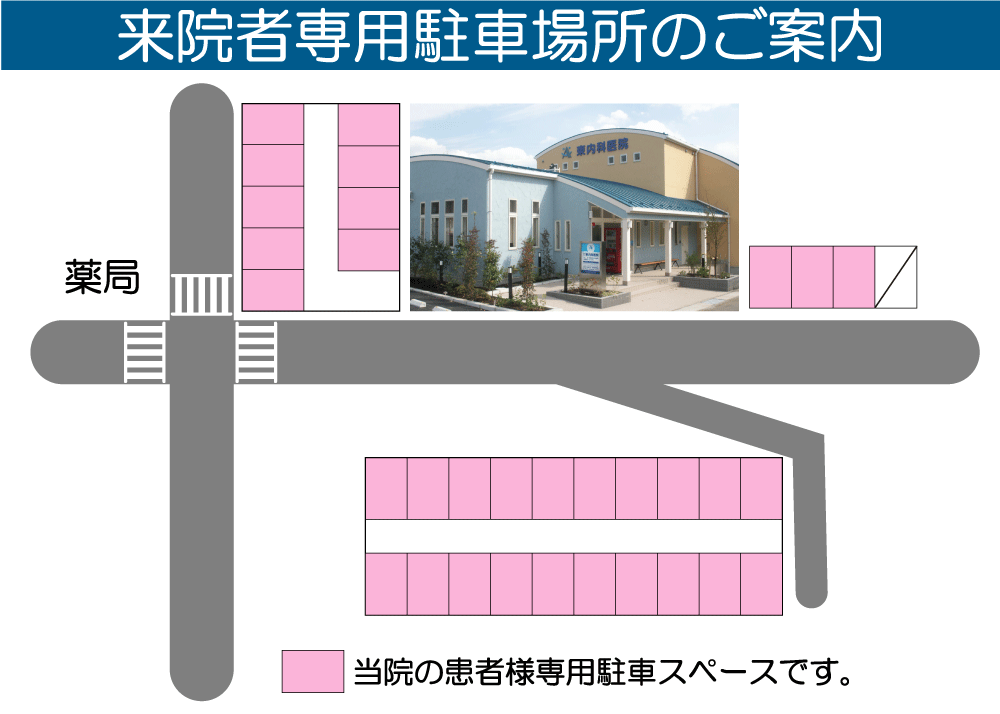
車でご来院の患者様へお願い